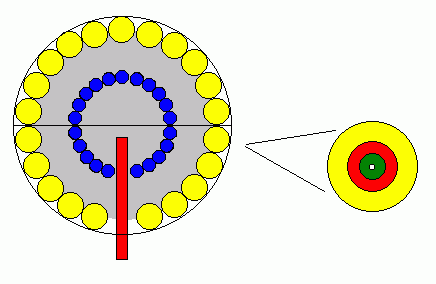
割物(芯物)花火の構造(断面)は左図のようになっています。
説明を簡単にするために図では色を付けてありますが、実際の割薬や星の外側は黒色をしています。
右の拡大図は、星の中の構造を表しています。
この図で言うと、上半分と下半分(導火線付き)に最初は分かれていて、材質は成形されたボール紙です。古き昔は、球状の木型の周りに新聞紙を張り重ね、それを半分に切って作っていたそうです。
玉皮の中には、目的に応じた星や部品を配置していきます。
その後、玉のサイズ、種類に合わせた枚数だけのクラフト紙を貼っていきます。丸い玉に貼るので、短冊状の紙を、極力重ならず、極力隙間が開かないようにして貼っていきます。そして、数枚貼り重ねたら天日で干し、目的の枚数になるまでこれを繰り返します。
玉貼りの途中で、導火線の反対側に竜頭(花火を吊るすための輪)を付けます。竜頭は、直接手で持ったり、紐や縄を付けて、玉を筒に入れる際に使用します。
星の構造は上図のように、ちょうどアメの変り玉のような構造をしています。菊用の星はこのように何色か使われていますが、牡丹用の星は普通1色のみとなっています。
一番の中心(芯)には菜種を使用するのが一般的で、水や火薬を溶いた水溶液で湿らせた菜種に、火薬の粉をまぶします。水分に見合った粉が付いたらまた湿らせて、火薬の粉をまぶします。
この作業と天日干しを延々と繰り返して、数mmの菜種が10号玉用の親星だと約3cm位までの大きさにします。
この作業を星掛けといい、途中で違う色に燃える火薬を掛けるので、空で色が変化するという訳です。図の例だと、錦色で広がり、紅から緑に変化します。
実際に空で燃える時は当然外側から燃えるので、星掛けは、空で出したい色変化の順とは逆の順で、色の火薬を掛けていきます。図の例だと、菜種に緑、紅、錦の順で作業することになります。
実際には、一番外側や、色の変わり目には、着火性を良くするために別な火薬が掛けられます。
芯星の場合は、牡丹物のように1色のみか、2色に変るくらいが一般的です。
図で言うと灰色の部分で、星と割薬の間は薄い和紙で仕切られています。
割薬の芯は、米の籾殻、くず米、綿の実、コルクなどを、玉の大きさに応じて使い分けています。
また、芯星の内側の割薬と、親星の内側の割薬には異なるものを使用しています。
花火玉の導火線は、打揚筒の中から打ち出される際に、筒の中の打揚火薬から二次的に点火されます。花火玉は上空へ向かいながら導火線も燃焼し、上空で玉がちょうど静止した頃に、玉の中心の割薬に点火するように調整されています。
玉詰め方法には、パックリと、八重芯以上の玉詰めで使用される本詰め(まる詰め、天井詰め)による方法があります。
パックリは、それぞれの半球に星や割粉を詰め、それぞれを両手に持ってパカッと合わせます。10号玉でもこれをやります。最初はとっても緊張し、必ず星の数個がすっ飛びます。下手をすると、詰めた全てが水の泡となります。
本詰めは、予め中の芯部分だけを球状に作っておきます。次に、玉皮の下半分にだけ親星を並べ、その中心に芯を置きます。そこへ、河童の皿のように、中心に丸く穴をあけた上半分の玉皮を置き、上下の玉皮をくっつけてしまいます。上半分の玉皮には、上にあけた穴から手を入れて親星を並べ、並べ終わったら、穴をふさぎ完成です。
紅(赤のことを業界では紅と表現します)なら炭酸ストロンチウム、緑なら硝酸バリウム、青なら硫酸銅などの薬品が使用されています。
また、アルミニウム、チタン合金、マグネシウムなどの金属粉を混ぜて使用することもあります。
あと、特殊な配合によって、点滅するような星や、パチッ、バリバリと破裂するような星もあります。
話がそれますが、手筒花火のあの暖かいオレンジ色の光は鉄粉によるものです。だから、あの手筒花火の火の粉は、ただの火の粉ではなく、焼けた鉄粉も降ってきているんですよ。
昔は寸、尺で呼んでいたのですが、尺貫法廃止の苦肉の策で、1寸を1号と表現しています。
2号玉(2号玉) : 直径 約6cm
3号玉(3号玉) : 直径 約9cm
:
10号玉(尺玉) : 直径 約30cm
20号玉(2尺玉) : 直径 約60cm
:
国内ではこのサイズを使用していますが、海外ではインチサイズの玉が使用されています。
| ・割物 | ・椰子 | ・型物(土星) | ・型物(ハート) | |||||
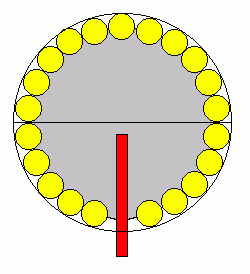 |
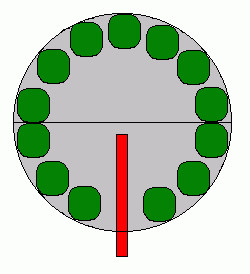 |
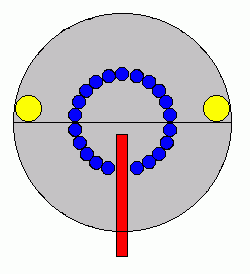 |
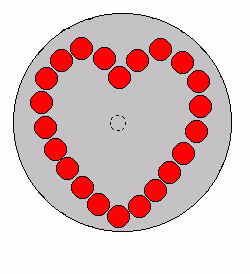 |
|||||
| ・万華鏡 | ・蝶 | ・千輪 | ・(参考)ポカ物 | |||||
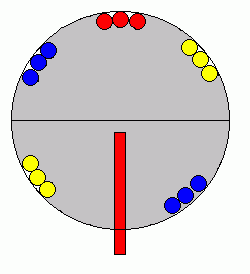 |
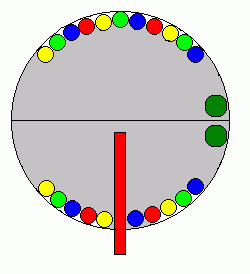 |
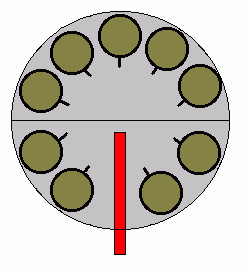 |
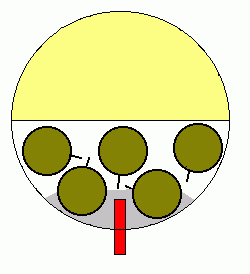 |
|||||
芯物:最初の図のようになっています。
割物:芯が無いだけで芯物と同様です。
椰子:星の種類と大きさが違うだけで詰め方は同じです。
土星:親星の配置を除き芯物と同一です。
(土星は、下の玉皮の芯星を無くすと、麦わら帽子になります)
ハート:ハート型そのものです。
万華鏡:サッカーボールの黒い所だけに星を置いたと思ってください。
蝶:羽と触角に分けて異なる星を詰めます。
千輪:星の代わりに部品が入っています。
(参考)ポカ物:
半皮に少量の割薬と部品が詰められ、もう半分は緩衝材だけです。
打ち揚がった花火を見ると、いったいどうやって花火の中にあの形を入れてあるんだろうと不思議に思うことだと思います。
実はそれが思ったよりも単純で、しかし奥が深いものなんです。
花火玉(割物)が上空で破裂するのは、導火線から割薬に着火し、瞬時に玉の中心から玉皮方向に火が回り、玉皮内の圧力が増し、玉皮の強度を超えたところで玉皮を砕き、中心から球状に膨張して広がります。
その膨張に乗って、中に詰めてある星も、燃焼しながら外側に向かって飛んでいきます。花火の原理は、全てこれで説明できます。
そうなると、見え方の違いは、使用する星の配合、大きさ、配置、玉貼枚数の違いによるということになります。
・星の配合としては
色の配合は、基本的にただ色を出しながら燃焼するものです。
(牡丹物、型物、菊物の芯星や親星の後半部分に使用されます)
錦の配合は、残光を残しながら燃焼するものです。
(菊物の色が出るまでの部分がこの配合です)
(錦かむろは、燃焼を遅くし、残光も増やします)
椰子の配合は、錦よりも残光をたくさん出すものです
(明るさを出すために、星も大きく作ります)
(色椰子といって、色で残光を残すものもあります)
その他に、点滅したりするような配合もあります。
・星の大きさは、明るさの違い、燃焼時間の違いとなって現れます。
・星の配置は、球の中心に近く置くか、玉皮に沿わせて外側に置くかで、広がり具合が異なります。
また、牡丹、菊、椰子の星を組合わせて配置することで、残光の有無をうまく利用しています。
・玉貼枚数は、膨張圧力との兼ね合いを決めるファクターで、玉のサイズと割薬の強さで決まり、そうそう変更するものではありません。
カムロのような垂れる花火は、星が適当なところで垂れるような貼り枚数に調整してあります。そうでないと、かむろではなく菊物になってしまいますから。
なんとなくイメージが沸いてきましたか。
本によって書いてあることもまちまちですし、花火業者によっても(※)多少違っています。また、なかなか正確に測定もできませんしね。
そこで、だいたいの目安として良く言われるのが以下の簡易式です。
開発中心高度 = 花火玉の大きさ(号数) × 40 (m)
開花直径 = 花火玉の大きさ(号数) × 30 (m)
実際には、大きい玉になるほど開発中心高度は少しづつ低くなりっているようです。(10号玉で三百数十mくらい)
まあ、あくまでもの目安ですから、この程度と考えてください。
(※)ちょっと脇道
同じサイズの玉(開発直径が同じ)なら、低いところで開花させた方が1サイズ大きな玉に匹敵する効果が得られるし、開発高度が低いと導火線の長さも、打揚火薬の量も少し節約できますから、低くしている業者もあるようです。
打揚煙火は法律上、上空20m以上で開かせれば良いことになっています。開くとはいっても、20m以下には燃えた星が落ちてこないように、という規制です。
本来はそうしないといけないのですが、錦カムロなどはいっぱい垂れた方が客には喜ばれるので、たまには地面まで落ちてしまうこともあります。そうなると主催者、警察、消防、当の花火屋は・・・(^_^;)。
その規制があるので、水中花火や地上花火は、打揚煙火と同じ玉を使用していても、分類上は打揚煙火ではないということになります。